昭和100年に、Leica A型で盛大にやらかした話

ライカA型と、昭和100年の冬春を撮影してみた。
気がつけば、今年は「昭和100年」。そんなワードをちらほらネットでよく見かけた。
そんな節目の年に、わたしは100年前に生まれたカメラ――ライカA型を手に取りました。
戦前どころか、まだ日本にラジオもテレビもなかった時代。そんな頃に、すでに35mmフィルムで写真を撮ろうと考えていたドイツ人がいたなんて、ロマン以外の何物でもありません。
しかもアナログカメラとして難易度の高い、このA型を使いこなしていた人が多くいたことも、想像するだけで頭が下がります。
そしてその100年のものフィルムカメラはただの骨董品じゃない。今でもちゃんと撮れる現役のカメラです。
でも、ちゃんと撮るには、こちら側の腕と覚悟が相当必要なんだなと……3本のフィルムで思い知らされることになります。
わたしの初めてのバルナックライカ、ライカA型の失敗とプチ成功の様子をお見せしていきます。
Leica(ライカ) A型とは

1925年、ドイツ・ライツ社が製造を開始した世界初の量産型35mmカメラ。小型軽量のボディとフィルム巻き上げ方式により、現代のスナップ撮影スタイルの原型をつくった存在です。
搭載レンズは沈胴式のElmar 50mm F3.5。ファインダーは独立式で、距離計はありません。ピント合わせはすべて目測。数字と勘と経験がものを言います。
スペックだけを見れば、今のカメラと比べて不便さばかり。でも、不便だからこそ、一枚一枚に時間をかけて向き合える。そんなカメラです。
……とは言っても、まずは写ってくれないと始まらないんですよね。
1本目:ピントが合っていない。というか、レンズが出てない。

初めてのバルナックライカ。そして、初めての大阪観光。
大阪城、道頓堀のグリコ、アメ村の雰囲気、通天閣のふもとのうどん屋。歴史と喧騒が入り混じる街で、古いカメラで今を切り取ろうとしていました。
でも――
現像してもらい、写真を確認する前にビビッと思い出しかのように
「あれ…もしかして沈胴伸ばすの忘れてたかも!?」と恐る恐る見たら…
すべてのカットが盛大にピンボケ。

原因は……沈胴レンズを伸ばすのを忘れていたこと。

ちなみにこれが本来、撮影モードの状態。しっかりと沈胴レンズを引き出して撮影します。

こちらが私が実際にやってしまったミスです。写真を確認する寸前で気づくなんて…。
バルナック使いなら誰でも通る道ですか?それともあまりにも下手すぎます?
フィルムカメラを売っている身としてものすごく恥ずかしいのですが、
思い切って失敗した写真をSNSに載せたら意外と反応がよくて、イイネがたくさん。
こんな失敗写真なかなか見られるものではないし、ある意味注意喚起として伝わればOKです。

ちなみにこの写真は、大阪城です。笑
2本目:フィルムが……巻けてなかった。
「今度こそ!」と気合を入れて臨んだ2本目。レンズも出した。露出も考えた。シャッターも軽快。
でも……「あれ、全然撮り終わらないな…」
「そういえば巻き上げの感触が軽かったような…」
「仕方ない、一回全部巻き戻しちゃうか…スルッシュポッ」
「え、早すぎるぞ?」
そこですべてを悟りました。ああ、またやらかした。
原因は、単純。
フィルムがちゃんと装填されていなかった。
バルナックではフィルムの先端を長く切るか、薄いカード使って、フィルム装填してスプールに深く差し込む必要があります。
今回はそれが甘く、うまく巻き込まれていなかった。
つまり、36枚分、空シャッターを切っていただけ。
春がもう少しの冬の夕方の公園で、虚無感と無力感でLeica A型を眺めていました。
3本目:ようやく撮れた。でも、なんか違う。

三度目の正直。
今度は準備万端。レンズも出した。フィルムの装填もOK。巻き上げの感触も問題なし。
慎重に、丁寧に、1枚ずつシャッターを切っていきました。
今回の現像が一番緊張して、怖かったです。
現像してみると……ようやく写ってた!ホッ
でも、写真を見ると、狙った構図よりも下が切れているものばかり。




理由は、ファインダーと実際の写りに微妙なズレがあること。
運よく切れることなく撮れた写真もありましたが、ファインダー内の画角を信じすぎました。

恐らく知識のある方なら、ファインダーはあくまでも補助的な役割というのを知ってると思います。
縦構図なら、わりと撮れていました。




100年前のライカA型を使いこなせるだけの実力がまだまだないことを痛感した3本目でした。
それでも、このライカA型を使いたくなる理由
3本中、2本が失敗。1本は成功半分。
写真としては惨敗。
でも、経験としては大きな収穫でした。
なぜなら、
「こんなに不便なカメラを、戦前から今まで、愛し続けてきた人がいる」
という事実に圧倒されたから。それも世界中に。
人によっては、代々ライカA型を子ども、そしてそのまた子どもへと受け継いでいく。
それくらいバルナックライカ、ライカA型の価値の高さはほかのカメラよりも高いのです。
使い方もそう。
ピントも、露出も、フィルム装填も、すべて自分でやらないといけない。
でも、その不便さの中に「写真を撮る」という行為の本質が詰まっている気がしました。
撮っているのではなく、私はまだ撮らされている立場というのも再確認しました。
まとめ
昭和100年の今年、100年前のカメラを通して思ったのは、
「人が写真を撮る理由」は、案外100年前から変わっていないのかもしれない、ということ。
目の前の光景を、大切に切り取りたい。
フィルムが進まずとも、ピントが合わなくても、またシャッターを切りたくなる。
そんな魅力が、Leica A型には確かにあります。
次こそは、構図もピントも決まった「一枚」を撮ってみせる。
そんな静かな決意を胸に、今日もElmarを伸ばして、そっと巻き上げます。
関連記事
-
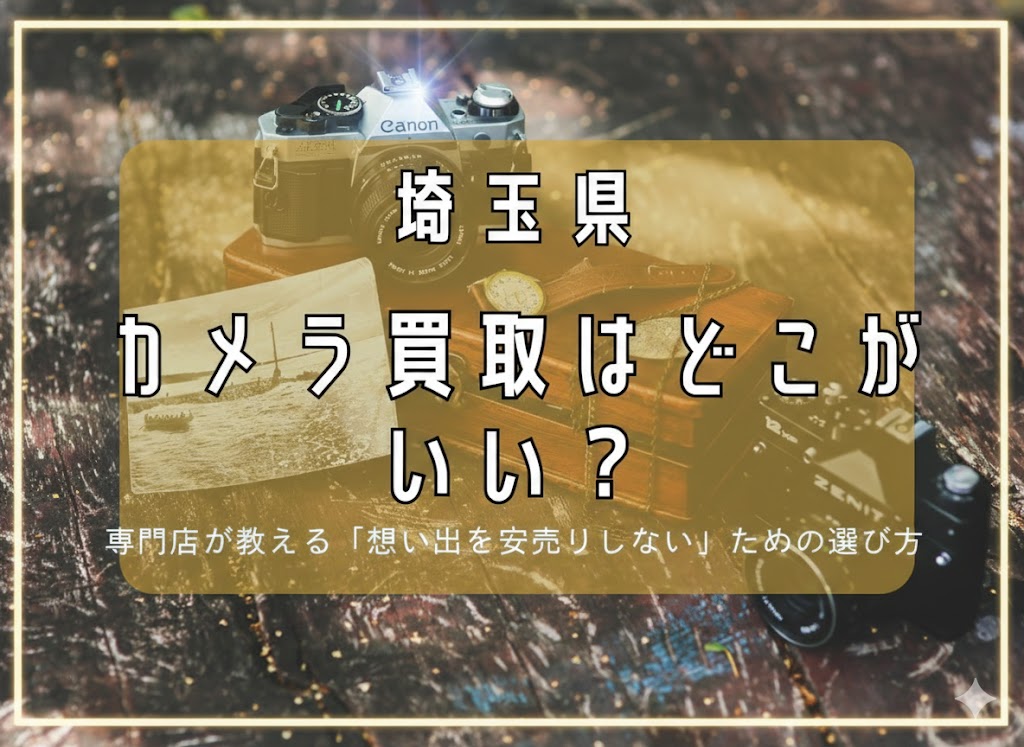
【埼玉県】カメラ買取はどこがいい?専門店が教える「想い出を安売りしない」ための選び方
2026.02.09 Infomation -お知らせ- -

捨てないで!実家の古いカメラが「お宝」に変わる3つの見分け方
2026.01.26 Infomation -お知らせ- -
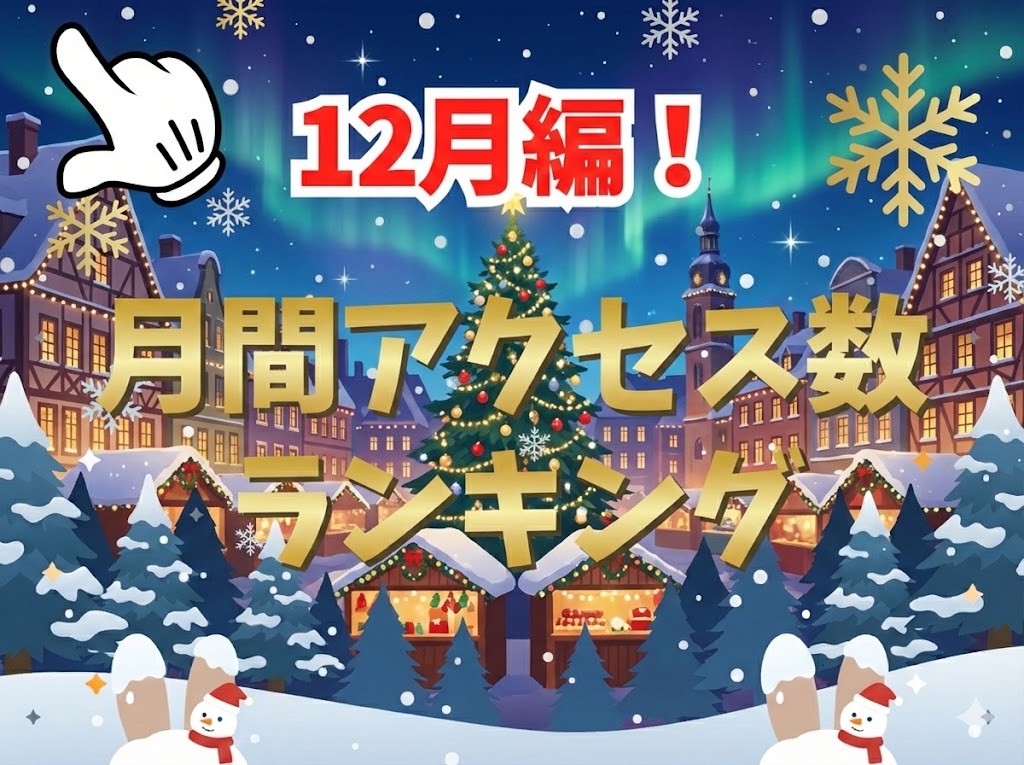
【2025年12月版】中古フィルムカメラ人気ランキングTOP10|サンライズカメラ月間アクセス数まとめ
2026.01.19 Infomation -お知らせ- -
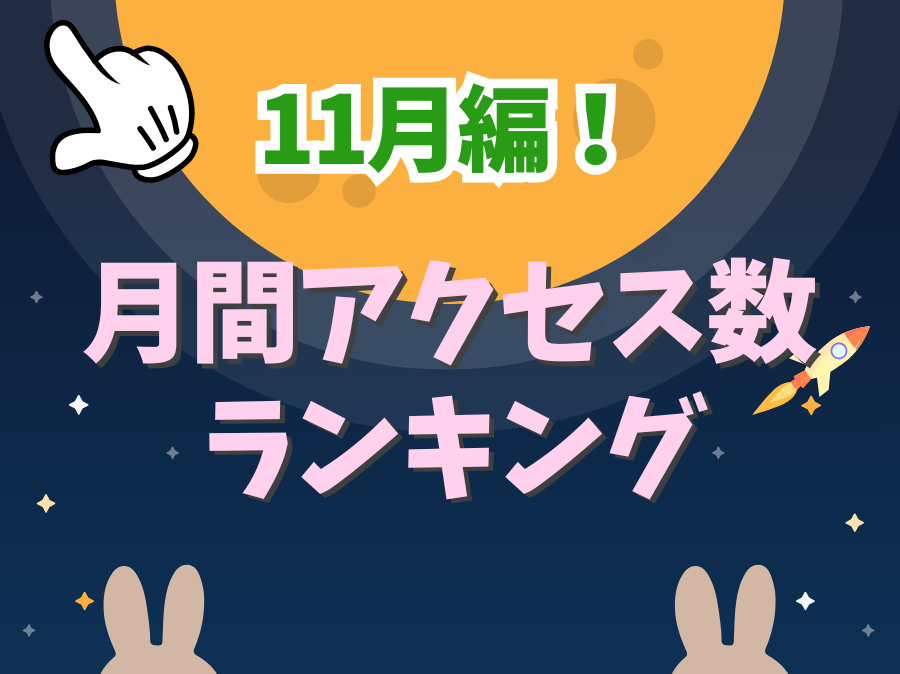
【2025年11月版】中古フィルムカメラ人気ランキングTOP10|サンライズカメラ月間アクセス数まとめ
2025.12.22 Infomation -お知らせ- -

フィルムカメラを高く売る方法|買取査定がアップする事前準備10選と専門店への伝え方
2025.12.08 Infomation -お知らせ-
